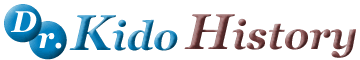日米医療事情くらべ(1)
 家庭医の誕生
家庭医の誕生 
保健同人社「暮らしと健康」1982年5月号掲載
ベン・ケーシーの国から見た日本
ひと昔前、「ベン・ケーシー」とか「ドクター・キルディア」とかの一連の医者もののテレビドラマがあったのを覚えておられるだろうか。なかなかよく出来たドラマで、私もファンの一人で欠かさず観ていたように思う。その頃、私はまだ中学生で、将来医師になるか、あるいはなれるかも分からない状態だったが、脳外科医ベン・ケーシーが、眼底鏡片手に、患者を診察しながら、苦味走った顔で警句を吐く度に、漠然とであるが、アメリカ医学に羨望を覚えたものだった。
今から思えば、たわいのない一中学生の夢であったが、60年代前半のアメリカはまだ日本い比べ、すべてにおいて巨人であった。それから十数年たった現在、私はニュー
ヨークの病院で、ファミリー・プラクティス(以下、家庭医療学科と訳す。)のレジデントとして働き、かつ学んでいる。レジデントというのは、専門医になるまでの修業期間中の医師のことを指すのだが、このレジデント修業の厳しさは、ケーシー、キルディアの頃とまったく変わっていないようである。
しかし、この十数年の間に、日米の国力、特に経済力の差は、驚くほど縮まってしまった。アメリカの経済力の衰えは、もちろん医学の分野にもそのしわ寄せをのばしている。それでもなおかつ、アメ
リカ医学は総合的にみて、世界一であると言えよう。ここでわざわざ総合的にと断ったのは、何もすべてにおいてアメリカ医学が優れているわけではないからである。例
えば、日本の医学技術あるいは、制度の方が優れている分野もいくらかはある。
日本から離れて、1年半ニューヨークで暮らしていると、不思議なもので、日本のことー主に私の世界である医学に関してだがーが日本にいた時以上に正確に見えるようになってきた。また反対に、こちらでは外国人として生活しているため、アメリカのことについては、アメリカ人よりより客観的に判断できると思うのである。岡目八目というやつである。
そういうわけで、これから4回にわたって、アメリカ医学のいろんな面をとらえなが ら、それらを日本の現在の状態と比較し、日本が送れていると思われる点については、
どうすれば改善されるかといったことを考えていきたいと思うのである。
専門医ばかりが増えすぎて・・
先に、私は家庭医療学科のレジデントであると書いたが、この家庭医療学科の誕生は、米国の臨床医学の発展の歴史において、画期的な出来事であった。
この国では、内科、小児科、外科、あるいはもっと細かく、内科の中の循環器科などといったような専門科を標榜するためには、医学校業後、3年なり4年なりのレジデン
トと呼ばれる修業期間を各専門科で過ごし、その後、専門医試験に合格することが必要とされる。だから、ある医院を訪ねて、看板に循環器科と出ていれば、まず心臓に関しては安心して診てもらえるわけである。
専門医たちは、皆、自信と誇りを持っていて、診察室には例外なく、専門医試験の合格証が額に入れられて麗々しく飾ってある。患者の側の専門医に対する信頼も高い。
それはそれで、別に悪いことではないのだが、ここでもう少し、この医学の専門分化について突っ込んで考えてみよう。
人間歳がいくと、体のそこここに不調が出てくるのが常で、一人の人間が4つ5つの病気を抱えていることは、別に珍しいことではない。例えば、ここに、70代の高血圧と心不全と糖尿病を持った患者がいるとする。この患者の高血圧と心不全は循環器科が
診ている。糖尿病は内分泌科である。糖尿病性網膜症があるので、眼科も必要だ。足に糖尿病性の潰瘍ができたので、足の専門科も必要になる(実際にポダイアリストといって存在する。)。
要するに、満足のいくー何をもって満足とするかは難しいがー治療を受けるために、おびただしい数の専門医を要するということになる。そして、あげくの果てには、ノイローゼに陥り、精神科を最後に訪れるということになる。
一方、医師の側は、社会的な地位、報酬などと求めて、ますます専門家志向を高めて いった(少なくとも十年前までは)。かくして、医師は患者を診るというよりも、各臓器を診るといった観を呈するようになってきたわけである。国全体の医療経済とい
う観点からみても、これ以上の専門分化は許容を超えていた。
専門をもたない専門家をめざして
そこで十年前に登場したのが、家庭医療学科である。これは、一口で言ってしまえば、非専門の専門家である。もちろん米国にも、専門家でないいわゆる「家庭医」は以前
から存在したが、その多くは十分な卒後の医学訓練を受けていなかったしーというよ り、専門家以外に対する訓練そのものが存在しなかったーそのために、「家庭医」は、専門医に対してある種の劣等感を抱いていた。こういうことを、患者は敏感に感じ取
るので、ますます専門医の方に患者は流れることになる。悪循環である。
現在の日本の多くの開業医は、まさに同じ状況に置かれていると思う。日本では、この患者の専門医志向、あるいは権威志向に応ずるために、多くの医師は、たとえ将来開業して「人間」を診る予定であっても、医学部卒業後の5年、6年を「医学博士」の肩書きをとるために「ネズミ」を相手にして暮らす。このことが、いかに日本の臨床
医学の訓練、ひいては全体の発展に悪影響を与えているかは、後にもう少し具体的に 述べることにする。
さて、この従来の「家庭医」を、いかにして非専門の専門家に育てるかということで あるが、家庭医療学科では、われわれは3年間、レジデントとして訓練を受ける。その内容は多彩で、内科、小児科、産婦人科、外科、精神科にまで及んでいる。これらの主に、病棟においての訓練と平行して、家庭医療学科の外来で、3年間継続して、患者を診てゆく。この外来は、将来われわれが実際に家庭医として活躍する時のこと
を想定して、出来るだけ家族ぐるみで患者を診るということになっている。
私が現在持っている家族で、ひいおばあちゃんから、ひ孫に至るまでの4世代にわたる家族がある。医学的なことに関連して、家庭の中での一人の病人が、家族全体に非
常な影響を与えたり、また逆に、家族がその家族の一員に影響を与えて、病気をひき 起すといったことがよくある。このような場合には、家族全体を治療するために、家族とわれわれ主治医とその方面の専門家が集まって、ファミリー・セラピー(家族治療)というのをすることがある。
7年毎の試験で医師をチェック
このようにして3年間の訓練を終えると、専門医試験があり、これに合格すれば、晴れて家庭医専門医になるわけである。この家庭医療学科が他の専門科と異なっている点は、訓練自体の他にもある。それは、そのアフターケアのよさである。他の科では、専門医の資格を取ってしまえば、それは一生有効なわけだが、家庭医療学科では、専門医になった後も、7年間に一度再試験を受けなければならないのだ。
この十年間で、家庭医療学科もようやく米国において根を下ろしてきた。ほとんどの医学校がこの科を持つようになってきたし、一般の人々の理解も出来てきたようであ
る。出来た当初は、無医村のような所で働く医師という考えが強かったが、現在では、 ニューヨークのような大都市における家庭医も見直されてきている。
日本は今や専門医花盛り
さて、今度は振り返って、わが国の現状をながめてみよう。日本でも、今や専門医志向は花盛りである。専門医にあらずんば医師にあらず、といった観さえある。この意味では、十年前のアメリカの状況と似ているのだが、家庭医療学科誕生前のアメリカと比較してみても、日本の方が旗色が悪いように思える。とい
うのは、日本での専門医というのは、まず第一に一般的な訓練を受けた後に、専門的 な訓練を受けるといった形ではなくて、医学部卒業後、いきなり眼科とか耳鼻科といった専門医へのコースをたどることが多いので、専門医が極端に、その専門以外の一般的医学知識を欠いていること。第二に、各々の専門に関して、全国的に統一された訓
練の機関もなく、またそのチェック機関となるべき専門医試験というのも、未だにごく少数の科に限られていることである。
町の小さな医院の看板に、6つも7つも専門科が書いてあることがあるが、実際の話、多くの科は、別に特別なトレーニングを受けなくても自称できるのである。再び話をアメリカに戻すと、家庭医療学科といったものができる以前でも、卒後、一般の訓練を受けてから次に専門に移るというのが原則であった。だから、内科、外科というような大きな科の専門の一分野を選ぶ前には、数年間の一般内科、一般外科の訓練が義務づけれれているし、眼科、耳鼻科といったより特殊な科でも、ほとんどの場合、卒後一年目のインターンは、一般外科を回る。
「白い巨塔」さながらの封建性
総論的に、日本の卒後教育の問題点を述べたが、これからの話との関連もあって、も う少し具体的に日本の卒後教育が、どんな風に行われているかを書いてみよう。
先にインターンという語が出たが、これは日本では現在死語である。現在は、医学部卒業後、国家試験に合格すると、大多数は、2年間を「研修医」として過ごす。しかし、その研修の内容は、先に述べたように一般から特殊へという形ではなくて、最初
から特殊な専門科に入る場合が多い。
これには、日本の研修指定病院の大部分が大学付属病院であることが大いに影響していると思われる。
1978年の統計によると、80%が大学付属病院になっている。日本お 大学医学部というのは、大学の中でもっとも封建的な部分を多く残した学部である。
だからこそ、あの60年代の大学闘争の火ぶたを切ったのは、東大医学部だったわけで ある。しかし、あれだけの犠牲を払いながら、変わったことといえば、インターンがなくなり、研修医という制度(しかも、義務でさえない。)ができただけである。医学部の体質というのは、本質的には旧態依然である。山崎豊子の「白い巨塔」という小説があるが、あれはあながち誇張であるとはいえないと思う。
医学部の各科には、教授を頂点とするヒエラルキーが存在し、内科、外科では、それがまたいくつもの講座に分かれてその各々に教授がいる。この一人の教授を頂点としたユニットを教室と呼ぶことが多いが、教室はその研究業績で評価されるので、それを上げることが義務づけられている。しかし、その研究の対象は、教室員が協議して
決めるといった種類のものではなくて、たいていはその教授の専門分野に自動的に決まってしまうのである。
大学病院で研修する場合、ほとんどの場合、どこかの教室に所属するという形をとるから、今まで述べてきた医学部のこの特殊性と、研修指定病院の8割が大学付属病院であるという2つの事実を考え合わせると、日本の卒後教育において、広い医学一般
の訓練を受けることが、構造的に不可能になっていることが分かっていただけると思 う。
| BACK
|