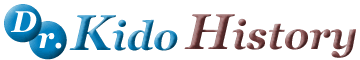パリ、アメリカ病院便り(9)
パリ、アメリカ病院便り(9) 
9)救急室

95年の春にパリに来て自分のアパートを借りる前に病院の宿舎に住んでいた時期が3か月ほどあった。その宿舎は日本流に言うと2LDKの一人暮らしには広すぎるほどのアパートで、本来は救急室勤務の医師あるいはレジデントの宿舎として作られたものである。したがって場所は病院の救急室のすぐ隣にある。筆者のそのアパートの横には救急医の休憩室があって、そこで彼らとよく雑談をすることがあった。都合のいいことに、救急室に勤務する医師は、スコットランド人とかアイルランド人とかの英語国民でフランス語もできるという人間なので、コミュニケーションにはまったく問題はなかった。また年令も30代の比較的若い医師なので何でも気安く聴けるということもあった。さてその中の一人のスコットランド人のM医師のことである。彼は、筆者個人とはよく世間話も交わすし仲だしうまくいっていたが、他の日本人科(Section
Japon、連載第3回参照)の職員たちの受けがあまりよくなかった。(予約外の患者は救急室を受診し、その際、日本人科の職員が通訳につく。)その第一の理由が彼の診療態度がやや投げ遣りだったことにある。例えば、風邪症状で熱もなく軽症であれば、どうもないの一言で薬もなしに帰してしまうといった具合である。彼との会話でうすうす感じたのだが、この態度は、救急室勤務そのものから来ていたようだ。救急室では医師の勤務体制もシフト制で、場合によっては夜勤が数日以上続くこともある。彼はそのような勤務を昨年知り合ったときにもう6年もやっていたのである。大げさに言えば「燃え尽き症候群」といったところだろうか。少なくとも、いい加減もううんざりしていたというのが本音だろう。その証拠に96年春に彼はここを辞めて母国のスコットランドに戻ってしまった。
かといって、アメリカ病院の救急室の仕事が、「アメリカ」の病院の救急室のように激務かというとまったくその反対である。筆者はレジデント時代をニューヨークはブルックリンの病院で過ごしたが、その救急室の戦場のような忙しさと比較すると、パリ、アメリカ病院の救急室は予約がないというだけで、優雅な普通の外来である。
その普通の外来が月に何回かだけ緊張するときがある。それは、アフリカや中近東で病気や事故にあい、現地での治療がままならないため、患者が空輸されてくるような状況時である。定期便ではない飛行機で来ることも多いので、数時間の時間のずれはしょっちゅうである。このような際には、24時間アラウンドザクロックで仏英バイリンガルの医師と看護婦がそこに存在しているということだけでもかなり役にたつ。筆者が当地で診療を初めてすぐの95年6月に、邦人旅行者がアフリカ旅行中、脳マラリアに罹患し、空路転送されてくるのに関与したことがある。夜中の1時に病院に到着するとの連絡だったが、日本大使館領事部の人と救急室の待合で待てども待てども到着しない。結局到着は午前3時前であった。救急室からICUに直行し、そこでの状態を確認し終わったら、夜が白々と明け始めていたのを覚えている。当アメリカ病院の救急室を、その他の世界中の救急室と比較しての一番の特徴は、このように、医療過疎の、ヨーロッパの周辺国を含めたグローバルな地域の救急室の役割を果たしていることではなかろうか。
さて、救急室というと忘れられないエピソードが一つある。95年の冬のことであった。週末の夜、アパートでくつろいでいると救急室から電話がかかってきた。筆者には救急当番の義務は無いので、自宅に電話がかかるということだけで尋常ではないことが発生していることが容易に想像された。その直感は見事に当たっていた。研修旅行中の日本人女学生がホテルで首吊り自殺未遂をして、救急室に運び込まれたが、まったくしゃべろうとしないので、何とか日本語でコミュニケーションをとってもらえないかということであった。急いで駆け付け、対面してみると確かに能面のような表情を崩さず、ほとんど一言もしゃべらない。そこで部屋を出て、付き添いの友人達から自殺の直接原因は旅行先ですりにあってからしょげかえってしまったこと、その遠因として考えられるのは学業不振と男友達との関係の悪化ではないかといった情報を得た。この情報をもとに、冗談を交えながらこちらから問い掛けを続けると、少しづつしゃべり始め、お腹が減ったと言い出した。そこで、キャフェテリアでサンドイッチと飲み物を買ってきて与えると、おいしそうにむしゃむしゃ食べ始めた。その様子を見て筆者もほっとしてしまい、それまで交代でずっと横に付いてくれていた患者の友人の一人と診察室を出て、患者一人を残し廊下で数分会話していた。するとその時突然、診察室の中からガシャーンという大きな音が聞こえた。あわてて診察室に飛び込むと、患者は引っ張ってきた椅子を台にしてかなり高い位置にある窓からまさに飛び降りようとしていた。大声で引き止めたが、そのまま飛び降りてしまったので、他に方法はないので筆者もその後から飛び降り数十メートル先の病院の敷地内で何とか追い付くことができた。その時の患者の思いつめたような表情から察するに、救急室が一階ではなく四階、五階にあっても飛び降りていたことは間違いないだろう。結局、この患者は精神科病棟のある病院に法定入院してもらわざるを得なかった。
もう肌寒い夕暮れの帰宅時、救急室の横を通るときこんなほろ苦い体験が思い出される、パリの秋である。
| BACK |