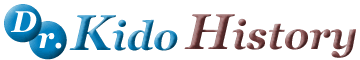短期集中連載 もうひとつの米国レジデント物語
第1回
50年代から70年代
(医)木戸医院 木戸友幸
これまで米国のレジデンシーについては,さまざまな書物や報告での紹介がなされてきた。筆者自身も80年代前半に,ニューヨークで家庭医療学(Family
Practice) のレジデンシーを経験したこともあり,文章,講演を含め数えきれないほどの紹介をしてきた。これらの米国レジデンシー紹介において,語られるのはほぼ100%,その
「光」の部分であるように思われる。例えば,指導体制のよさや,経験できる症例の多さ,教育プログラムの質の管理体制があること等々である。トレーニングの過激さ
さえも,それを乗り越えたときの自信や,自己の限界を知る手段として有用などの観点から美化されてきたようである。
これらの紹介により奮起した若手医師が渡米し,優秀な臨床家や教育家に育ち帰国 したという経緯からみて,この「光」に焦点を絞った紹介も有益ではあったようである。翻って,米国の医学教育界の現在の動向をみてみると,現状の制度に関しては必ずしも満足していないように思われる。
2004年から日本でも,卒後研修が義務化されることになったが,その際参考にされるのが,日本ではもっとも多く紹介されている米国のレジデンシー制度であることは間違いない。このとき,米国レジデンシー制度の持つ「影」の部分を知らずに無条件に何でも取り入れてしまうと,後に禍根を残すことになりかねない。
このため,今回,米国のレジデンシー制度を,その成立した第二次大戦後から振り返って考察してみたい。「光と影」の両方を紹介できればいいが,「光」はすでに語
り尽くされているので,本稿では当然,「影」の描写が主体になるであろう。
戦後の混乱を収拾して,社会が落ち着き始めた50年代は,米国の「高度成長期」に当たるのではないかと思われる。医療の分野でも,卒後のレジデンシーが一応整ってくる。しかし,この時代はレジデンシーを経験しない,いわゆるGP(一般医)も数多く活躍していた時代である。レジデンシーを終了して,ボード試験に合格すれば誰も
がうらやむ専門医になれるのである。
したがってレジデンシー(特に1年目の以前インターンと呼ばれた期間)は,エリー ト医師になるための「通過儀式」という側面もあったようである。
「Intern」
この当時のレジデンシーの様子をもっとも忠実に描いた書物として真っ先に挙げなければならないのは,「Intern」である。この本は,匿名著者,Dr.
Xのものとされ,1965年に出版された。出版後,一般読者の大きな反響を呼び,ニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストに22週連続で載ったほどであった。
内容は,実際にインターンを行なったDr. Xが日々の出来事を帰宅後詳細にテープに録音し,それを妻がタイプして文章化したものと書かれている。したがって,この作品は純然たるドキュメンタリーで資料としての価値は高い。彼は,米国の某都市の
グレーストーン病院(これも仮名と思われる)で内科,外科,産婦人科,小児科を回るローテイティング・インターンを受けたのだが,この時の日々の訓練の厳しさ,その時代の医療の不完全さ(ほとんどの病気は診断は付いても治らない)などについて,具体的かつ克明に記録している。医師の過労が極地に達したときは,哀れな患者を前にして,シニカルな冗談を飛ばすといったことも書かれている。これは,80年代前半にレジデンシーを経験した筆者にもよく理解できる心境である。
60年代から日本人のレジデンシー経験者も現れ,それら先輩たちの報告も数々あるので,内容の詳細には至らない。大ざっぱに言えば,非常に過酷な訓練であったが,1年が終わると医師として素晴らしく成長を遂げたといった,きわめてポジティブな論旨である。その過酷さについては,「『ベン・ケーシー』や『ドクター・キルディ
ア』(いずれも当時流行った医者ものの連続テレビ・ドラマ)が幼稚園の劇に見えて しまう」という新聞評が,本の裏表紙に書いてある。
筆者がこの「Intern」について特筆したい点は,特に反社会的でもないドキュメンタリー本の著者が実名を隠して,匿名にした点である。この大きな理由は,その当時の米国の医療界がかなり閉鎖的なギルド的社会で,レジデンシーはそのギルドに入会するための「入会儀式」的な意味合いがあったからではないであろうか。少し,大げさな比喩を持ちだせば,秘密厳守のフリーメーソン(註)の入会儀式のようなものだろうか。
The harder,the better?
この時代のレジデンシーのモットーを一文で表すとすれば,「The harder,the better」(過酷であればあるほど,よいトレーニング)が一番適当なのではないかと思われる。筆者がトレーニングを受けた80年代前半は,内科系も外科系も3日に1度の
当直が標準であった。ということは,3日に1度,連続30数時間労働を義務づけられるということである。これだけでも十分厳しいのであるが,70年代までは,外科系の1年目レジデントは2日に1度の当直が標準であったそうである。それでも外科医は,
「2日に1度の当直の唯一の欠点は,自らの手で,半分の患者しか入院のワークアップをできないことである」と豪語していたそうである。
さて,こういう厳しいレジデンシーを,それを経験した医師はどう評価しているのであろうか?
研修医の労働条件に関する著書を著したある医療ジャーナリストと話をする機会があった。そのジャーナリストは,その本を書くために,全国の研修病院の指導医をインタビューして回ったという。その中には,米国でのレジデンシー経験者も数多くいた。そして,そのほとんどすべてが,かの地での過酷なレジデンシーを積極的に評価していたとのことであった。実際に筆者自身も,そういうインタビューを受ければ,自分がよりよい医師になるためには非常に役立ったと答えるだろうと思
う。
したがって,この時代のレジデンシーの評価を経験者の意見に頼ることは,あまり意味のないことのようである。誰しも,自らの体験を,それが過酷であればあるほど,意義の薄いものとは思いたくないものである。また,過去の体験は一般的にいって美化されるものである。
しかし,どの回答者も例外なく,「あの体験は2度と繰り返したくない」と答えたそうである。
(この項つづく)
註:中世以来の熟練石工組合を母体として18世紀初めイギリスで結成。啓蒙主義的精神を基調とし,現在では世界的に多くの名士を会員に含むとされるが,全容は明らかでなく,秘密結社的な要素が高いと言われる
参考文献
1)Dr. X:Intern. Harper & Row,1965(現在絶版らしい)
2)ブルックリン便り:http://www.carefriends.com/kido/newyork/index.html