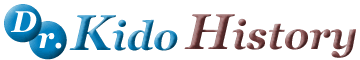|
家庭医木戸の現場報告(24)
2025年10月号 JECCS News Letter
外国語に関する諸々(もろもろ)
外国語の勉強は中学で英語の授業が始まった時から好きでした。高校に入学してからは、ベビーブーム時代のことですから、大学入試を目標に文法中心の授業で興味が薄れた時期も少しありました。しかし、英語教師の一人が教材に味のある短編小説を使い、きれいな発音で自ら読み下しながら、読解のコツを上手に説明してくれました。高校を卒業後1年間の浪人時代にこの楽しい英語授業を思い出し月一冊の割で英語の小説を、主に英英辞典を使って読むという自己流の英語学習を続けたのです。その結果、一浪後の大学入試では英語に関してはかなりの高得点を取ることがきできました。
医学部を卒業したら研究医ではなくて臨床医、それも米国でレジデンシーと呼ばれる臨床研修を受けようと計画を立てていたのです。当時は入学後の2年間は教養課程という比較的緩いノルマだったので、この2年間に授業が終わってから週3回、土佐堀にあるYMCA英語学校に通うことにしました。3回とも異なる米国人の教師が独自のユニークな方法で実用英語を教えてくれ「聞くと話す」の英語は2年間でかなり上達しました。少し傲慢かもしれませんが、英語はこれくらいにしておいてもう一つ外国語を学習しようと思い、3年生の解剖学が始まる時からフランス語(これも解剖実習の終わる夕方から週3回)を実家の近くに当時開校した大阪日仏学院で始めました。まったくの初級から初めて2年間で中級まで進級し、かなりの満足感がありました。
医学部卒業時(1977年)に米国レジデンシーに必要な留学試験に合格しましたが、中々行き先が決まらず、卒後3年目に何とかニューヨークはブルックリンの病院でFamily Medicine(家庭医療学)のレジデンシーに採用され、苦しくもあり楽しくもあった最高の3年間を経験しました。帰国後、大阪の国立病院で10年勤務した頃、東大医学部で国際交流の仕事している米国留学時代からの友人から連絡がありました。パリの国際病院からの依頼で、日本人医師で米国の医師資格があり、フランス語も理解できる医師を探しているとのことでした。この友人は私にフランス語の基礎があることを知ってくれていたのです。話はとんとん拍子で進み、1995年からの2年半、パリ郊外の国際病院で主に在留邦人相手に総合診療をする機会を得ました。
60代半ば(2016年)で開業医を辞め時間に余裕ができてからはフランス語学校の週1回の授業も再開しました。また英語とフランス語の小説やノンフィクションを昼間の空き時間に読み耽るという至福の時間も得ました。医学以外の英語の小説やノンフィクションは学生の頃から読んでいたのですが、フランス語のゾラ、パルザック、モーパッサンなどの19世紀の作家、カミュ、フロベール、モーリアックなどの20世紀初頭の作家の小説はこの歳になって初めて読みました。もちろん電子辞書片手にですが。でも、この読書は何かの試験を受けるための「勉強」ではなく、皆さんが碁、将棋、麻雀などを楽しむのと同じように「楽しみ」なのです。この楽しみは時間と電子辞書さえあれば一人ででき、一生続けられる楽しみです。
というわけで、若い頃の英語とフランス語の学習がその後の私の人生をどのように変えてきたかということをお話ししました。一つの外国語を知ることは、もう一つの文化を知るということです。これによって現実的に仕事面で役立つこともありますし、仕事をリタイアあるいはセミリタイアした後にも、その外国語が生んだ書物や映画などの無数の作品を死ぬまで楽しむことができるのです。この歳になって改めて10代後半に、自らの欲求に素直に従って英語、フランス語という外国語をしっかり学んで本当に良かった思います。
|