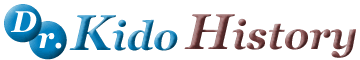ブルックリンこぼれ話(14)
ブルックリンこぼれ話(14) 
米国弁護士事情
ニューヨークに3年間住んでいた間に、弁護士にお世話になったことが一度だけあります。交通事故でろっ骨骨折を負い入院した時のことです。1年上級の女性レジデントの夫が駆け出し弁護士だったので、その上司を紹介してもらいました。病院から退院した直後のある日、彼は僕のアパートを訪ねてきました。
まず驚いたのは、米国の弁護士は着手料とか相談料とかを一切請求しないのです。すべて成功報酬です。弁護士報酬は、勝訴額の量によって違ってきます。額が少ないと、弁護士の取るパーセンテージが高く、額が多くなるにつれてそれが下がってきます。
僕の事故の場合、例によってダメ元で百万ドルの訴訟を起したのですが、結果として取れたのは、2万ドルでした。この程度の金額の場合は約50%が弁護士の取り分とな
ります。
こういう一連の説明の後、これも弁護士ものの小説や映画でおなじみのせりふが語ら れます。「この事件に関して、誰が連絡してこようとも、そのことに関しては弁護士を通して欲しいと答えてください。」実際は、こういう事態には遭遇しませんでしたが、そう言うときの弁護士はなかなか頼もしく見えました。
このように、手続き的にも金銭的にも、米国で弁護士と契約するのは非常に簡単なのです。また弁護士の数も米国では半端なものではありませんから、弁護士間の競争も苛烈です。そういうことが相まって、現在の米国の訴訟社会が生まれたようです。
このことを憂えているアメリカの一般市民は多いと思います。一般市民だけでなく、弁護士たちの中にも自己嫌悪に陥っている者もいます。そのことを題材にした映画の代表作は、80年代にポール・ニューマンが好演した「評決」(Verdict)です。この映画の中で、かつて敏腕だったニューマン演ずる弁護士が自暴自棄でアル中状態になり、救急車の後を追い回すような、事故漁りの弁護士に成り下がってしまいます。ところが、ある医療過誤事件を担当したときから、弁護士本来の役目に目覚め、勝訴に至るという筋です。
さて、現実にも僕の周囲で、最近ちょっと変わった米国人元弁護士に遭遇しました。以前からの知人で数年前まで米国で弁護士をやっていた米国人女性なのですが、2002年の夏、彼女が日本旅行に来た時に再会する機会があったのです。てっきりまだ弁護士をやっているものと思っていたので、「アメリカでの弁護士稼業の景気はどうなの?」と尋ねると、「私、もう弁護士辞めちゃったの。」と答えるではありませんか。
彼女によると、アメリカの司法制度にもはや正義は存在しない、あるのは悪しき資本主義の原則だけだと言うのです。ですから、司法の原則を重んずる彼女のような弁護士にとっては、その職業を続けることは自らの良心を裏切り続けることであり、苦痛以外の何物でもないのです。彼女は今何をしてるかって?米国東海岸の小さな街で、自家製のチョコレート屋さんをやっているそうです。これは本当の話です。
| BACK
|